絵の具って、使っているとどうしても中途半端に余ったり、カピカピに乾いてしまったりしますよね。
でも、「これ、どうやって捨てればいいの?」と悩んだ経験はありませんか?
実は、絵の具の種類や容器によって、正しい捨て方や注意点が変わってくるんです。
間違った処分は、環境に悪影響を与えるだけでなく、火災や事故につながることも…。
この記事では、アクリル絵の具や油絵具の違いはもちろん、容器別・自治体別の処分方法、さらに「捨てずに活かす」アイデアまで、わかりやすく解説します。
趣味や仕事で絵を描く方はもちろん、子どもが学校で使った絵の具を処分したい保護者の方にも役立つ内容になっていますので、ぜひ最後までご覧ください!
安全に絵の具を捨てる方法

固まった絵の具の処理方法
固まった絵の具は、基本的には「燃えるゴミ」として捨てられることが多いですが、念のためお住まいの自治体の分別ルールを確認しましょう。量が少なければそのままでも問題ありませんが、絵の具が大量に余ってしまった場合は、新聞紙やいらない布に包んでから袋に入れ、しっかり口を縛ってからゴミとして出すと、安全かつ清潔に処理できます。また、密閉容器に入れて一時保管し、数回に分けて処分するのも一つの方法です。
アクリル絵の具の捨て方
アクリル絵の具は水性ではありますが、乾くと固まってプラスチックのような状態になるため、扱いには注意が必要です。使い残しがある場合は、パレットなどでしっかり乾かしてから、固形状態で可燃ごみに出しましょう。絶対に液体のままシンクや排水溝に流さないこと。下水の詰まりや環境汚染の原因になる可能性があります。絵の具の付着した水を捨てる場合は、まず沈殿させて上澄みだけを流し、絵の具のカスは紙などに吸わせて可燃ごみに出すのが安心です。
15年程前からあるアクリル絵の具がまだ使えるか試しつつ枯れたのは捨てる選別してたんだけど、袋の中スプラトゥーンになってちょっと嬉しい。🦑🎨 pic.twitter.com/k7S6A2Y24r
— だーよめ (@Daayomedayo) February 13, 2025
油絵具やオイルの廃棄方法
油絵具やペインティングオイル、溶剤(テレピン油やペトロールなど)は揮発性が高く、有害な成分を含む場合もあるため、慎重に処理する必要があります。布や新聞紙に染み込ませて乾燥させ、不燃ごみまたは有害ごみとして出すのが一般的な方法です。ただし、自治体によっては危険物として特別回収になる場合もあるため、分別区分を事前に確認しましょう。空き缶に入ったままの溶剤や、揮発性が高く乾燥しにくいものは、自治体の清掃センターに相談するのが安全です。
自治体による絵の具の分別ルール

横浜市の絵の具処理ガイド
横浜市では、アクリル絵の具については中身をしっかり乾燥・固化させたうえで「燃やすごみ」として出すことができます。液体のまま排水口に流すことは絶対に避け、環境保全の観点からも固化が必須とされています。また、油絵具や溶剤(ペトロールやテレピン油など)は、揮発性や引火性の問題があるため、「有害ごみ」または「資源循環局に相談の上での特別回収」の対象となる場合があります。横浜市の公式サイトや「家庭ごみの出し方ガイドブック」を確認し、迷ったときは資源循環局へ問い合わせるのが安心です。
一般的な廃棄物と資源の分別
絵の具の容器は、プラスチック製・金属製・ガラス製などさまざまありますが、共通して「中身を完全に使い切る」ことが前提です。中身が残っていると分別先が変わるだけでなく、リサイクル処理が困難になります。プラスチック容器は、洗浄してから「プラスチック容器包装」へ。金属チューブは「金属ごみ」または「資源ごみ」に、ただし残った絵の具がある場合は「不燃ごみ」に分類されることもあるため、事前確認が重要です。
捨てる際のラベル確認
製品のラベルに「危険物」「引火性」「可燃性液体」などの表記がある場合、それは通常のごみとして捨てることができないサインです。特に海外製の絵の具や溶剤などは注意が必要で、国内の基準とズレがあることも。処分前には必ずラベルを確認し、不明な場合は製品メーカーのサイトや問い合わせ窓口で詳細を確認しましょう。また、子どもやペットのいる家庭では、誤飲や誤使用を防ぐためにも、保管・処分を慎重に行いましょう。
絵の具の容器別の処理方法

プラスチック製容器の廃棄法
アクリル絵の具や水彩絵の具などに使われるプラスチック容器は、基本的に中身を完全に使い切り、内部をできるだけ洗浄してから「プラスチック容器包装」として分別回収するのが適切です。汚れがどうしても落ちない場合や、ラベルが剥がれて材質が分かりづらい場合には、「燃えるゴミ」として出すことが許可されている自治体もあります。水道水で軽くすすぐだけでも、分別の精度が上がりリサイクルに貢献できます。
金属製チューブの処分方法
油絵具によく使われる金属製チューブ(アルミやスチール製)は、中身を完全に使い切った状態であれば「資源ごみ」や「金属ごみ」として出すことができます。チューブの口元に絵の具が残っている場合は、できるだけ取り除き、乾燥させることが推奨されます。中身が多く残っていたり乾燥が難しい場合には「不燃ごみ」として処理するのが一般的です。自治体によっては「危険ごみ」として扱われることもあるため、判断に迷った場合は事前に確認をとりましょう。
ガラス製容器の扱い
一部の溶剤や高級絵の具などではガラス瓶が使用されていることがあります。中身をしっかり出し切り、可能であれば洗浄したうえで「ガラス資源ごみ」として処分してください。瓶が割れてしまっている場合は、怪我防止のために新聞紙や厚紙で包み、「不燃ごみ」として出します。ラベルやキャップが金属製の場合は、取り外して別々に分別することが望ましいです。リユース可能なガラス容器は、洗って再利用するという選択肢もあります。
パレットや筆の処理方法

とりあえずの保存方法
使いかけの絵の具や洗っていないパレット・筆などをすぐに処分せずに保管しておきたい場合は、乾燥を防ぐ工夫が必要です。例えば、筆やパレットに付着した絵の具がまだ湿っている場合、ラップでしっかりと包んで空気を遮断する、または密閉容器に入れて保管することで、次回の使用時に再利用しやすくなります。また、冷蔵庫に入れて保存する方法もあり、特にアクリル絵の具には有効です。ただし、食品と一緒にしないよう、専用の保存スペースを確保しましょう。
家庭でのリサイクルアイデア
使い終わった筆は、絵の具が取れにくくなっても、掃除用ブラシや靴磨き、園芸用の道具として再利用することができます。パレットも塗膜を剥がして再塗装したり、下地材として別の工作に活用することができます。絵の具の容器も、小物入れやミニプランターとして活用するなど、アイデア次第で新たな用途が生まれます。子どもと一緒に工作として再利用するのも楽しく、環境にもやさしい取り組みです。
今回使ったパレット。
いつもの餃子のヤツ。 pic.twitter.com/5wSYkYVBag— 梢瓏@ (@syaoruu) March 18, 2025
トールペイントの廃棄管理
トールペイントで使用される塗料には、水性と油性のものがあり、廃棄の際には成分の確認が欠かせません。水性塗料であれば乾燥させたうえで可燃ごみに出せることが多いですが、油性塗料は引火性の危険があるため、しっかりと乾燥させるか、揮発させたあとに不燃ごみとして出す必要があります。使用済みの布やスポンジなども同様に処理する必要があります。多くの塗料メーカーでは安全な処分方法を公式サイトで案内しているので、不安な場合は確認すると安心です。
専用の回収ボックスの利用

地域の回収日と時間
絵の具の処分で困ったときに頼りになるのが、自治体が設けている「危険物」や「特殊廃棄物」の回収日です。多くの自治体では年に数回、回収イベントや拠点回収を実施しており、通常のごみ回収では対応できないアイテムを適切に処理できます。たとえば、溶剤入りの缶や揮発性の高い液体が残っている容器なども、このタイミングで安心して出すことが可能です。回収日や時間、対象物の詳細については、自治体の公式ウェブサイトや広報誌、地域のごみカレンダーで事前にチェックしておきましょう。予約が必要なケースや、指定場所への持ち込みが必要な場合もあるため、余裕を持って準備を進めることが大切です。
粗大ごみとしての申請
絵の具関係の道具や資材が大量にあり、一度に処分したい場合や、大型の容器・保管ボックスなどが含まれる場合は、「粗大ごみ」として扱われる可能性があります。特に、絵の具や溶剤が入ったままの大きな容器、専用のキャビネットやラック類などは、通常のごみ収集では対応できないことがあるため、粗大ごみ回収の対象として申請する必要があります。申請方法は自治体ごとに異なりますが、多くは電話やオンラインで申し込みが可能で、処理手数料の支払い方法(シール式など)についても指定があります。処分したい物の種類と状態を明確にしてから相談するとスムーズです。
不燃ごみにしてはいけない物
家庭ごみとしてつい「不燃ごみ」に分類してしまいがちですが、揮発性が高い液体や、有毒性を含む化学物質などは絶対にそのまま不燃ごみとして出してはいけません。こうした物質は、ごみ収集車や処理施設で火災や有害ガス発生の原因になる可能性があり、非常に危険です。特に、油性絵の具の残り、スプレー缶の中身が残っているもの、溶剤の液体などは、使用済みであっても慎重に扱う必要があります。必ず自治体の指定する方法で処理し、安全な環境づくりに協力しましょう。
安全に絵の具を扱うための注意点
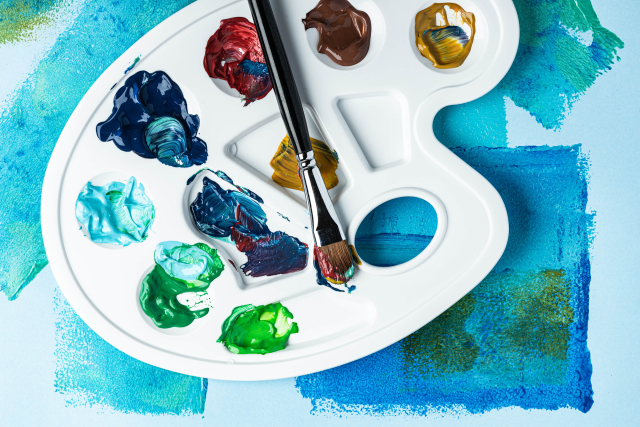
液体やスプレーの保管と処理
液体状の絵の具やスプレータイプの塗料は、揮発性が高く、温度や光に影響を受けやすいため、保管には十分な注意が必要です。使用後はしっかりとキャップやノズルを閉め、密閉状態を保ったうえで、直射日光を避けた涼しく乾燥した場所に保管することが大切です。とくにスプレー缶は高温になる場所(暖房器具の近くや車内など)に置かないようにしましょう。使い切るのが理想ですが、どうしても使いきれない場合は、内容物の残量に応じて適切な廃棄方法を選びましょう。缶に中身が残っている場合は、スプレー缶専用のガス抜きキャップを使って中身を出し切ってから処分するのが一般的です。
子供やペットへの影響
絵の具の中には、鉛やカドミウムといった有害金属を微量ながら含むものもあります。これらは摂取すると健康に悪影響を及ぼす可能性があるため、特に小さなお子さんやペットがいる家庭では、保管場所に十分な配慮が必要です。使用中も目を離さず、作業スペースの周囲に誤って口に入れそうな物を置かないなど、安全対策を徹底しましょう。誤飲や皮膚への付着があった場合は、速やかに水で洗い流し、必要に応じて医療機関に相談してください。
事故防止のための注意事項
絵の具やスプレーを使用する際には、必ず換気の良い場所で作業することが基本です。締め切った室内で使用すると、有害なガスが充満する恐れがあります。使用後は、フタを確実に閉め、手についた絵の具は石けんでしっかり洗い流しましょう。特に油絵具や溶剤は引火性があるため、作業中は火気を一切使用せず、火花が出る電気機器の近くでも使用を避けてください。また、廃棄処理の際も引火のリスクを考慮し、十分に乾燥させたうえで、自治体の指定する方法に従うことが必要です。
絵の具の残量を減らす工夫

少量の絵の具の使い方
絵の具は必要な分だけを小分けにして使用することで、無駄を減らし経済的に使うことができます。特にアクリルや油絵具は一度出すと乾燥や酸化が早いため、パレットに出す量は最小限にとどめましょう。残った絵の具はラップや密閉容器を使って空気に触れないように保管すると、次回も再利用できます。また、使いかけの絵の具は冷蔵保存することで乾燥を遅らせることも可能です。ただし、食品と一緒に保存しないように注意しましょう。
乾燥した絵の具の利用方法
乾燥してしまった絵の具でも、工夫次第で再活用できます。アクリル絵の具の場合、一度固まると元には戻りませんが、薄く乾燥したものなら水でふやかして「テクスチャ素材」としてコラージュやアート作品に使うことができます。水彩絵の具は少量の水を加えることで元に戻る場合が多く、固形水彩のように再利用可能です。チューブタイプで完全に固まってしまった場合でも、チューブを切って中身を取り出せば、絵の具の塊を削って粉状にして使用するなどの工夫もできます。
使わない絵の具の寄付先
使用予定のない絵の具がある場合は、捨ててしまう前に「必要としている人に届ける」選択肢も考えてみましょう。小学校や福祉施設、地域の児童館、アート支援団体では、絵の具や画材の寄付を受け付けているところがあります。また、NPO法人やアートプロジェクトの運営団体が、使いかけの画材の回収・再配布を行っていることもあるため、インターネットやSNSで調べてみるのもおすすめです。子どもたちや若いアーティストの創作活動に役立ててもらえる可能性もあり、絵の具を最後まで生かすことができます。
捨て方に関するよくある質問

家庭での指定ごみの種類
家庭で出る絵の具や関連用品の処分方法は、自治体ごとに分別基準が異なります。「可燃ごみ(燃やすごみ)」「不燃ごみ」「資源ごみ」「有害ごみ」など、細かい分類があるため、必ずお住まいの自治体の指示に従うようにしましょう。たとえば、乾いた水性絵の具は可燃ごみで出せることが多いですが、油性の溶剤やスプレー缶は有害ごみや特別回収対象となるケースがあります。また、容器に中身が残っているかどうかで扱いが変わることもあります。判断に迷った場合は、指定ごみ分別表やごみカレンダーなどを確認することが重要です。
自治体への問い合わせ方法
分別や処分方法に不安がある場合は、自治体の公式ウェブサイトや地域のごみ収集カレンダーを活用しましょう。多くの自治体では「ごみ分別検索」などの便利な検索ツールを提供しており、「絵の具」「溶剤」「スプレー缶」などのキーワードで該当の処分方法を調べることができます。また、問い合わせ専用の電話窓口やLINE・メール相談なども利用可能な場合があります。正確な情報を得るためには、迷ったら早めに自治体へ確認することが安全で確実です。
リサイクル可能な絵の具について
水性絵の具や自然素材を使用した絵の具の中には、環境負荷が低く、安全性も高いため、再利用やリサイクルに向いている製品もあります。乾燥させれば可燃ごみとして出せるほか、紙や布に再塗布して創作に活用することもできます。容器の素材がプラスチックや金属、ガラスなどの場合、それぞれ資源としてリサイクルできるかどうかも確認しましょう。また、一部のメーカーでは使用済み容器の回収プログラムを設けていることもありますので、製品パッケージや公式サイトを確認するのもおすすめです。
絵の具の保管法と処分時期

湿気から守る保管方法
絵の具は湿気や直射日光に弱く、劣化や分離、カビの原因となるため、保管環境には特に注意が必要です。風通しの良い涼しい場所を選び、しっかりとフタを閉めて密閉状態を保つことが基本です。特に梅雨時期や湿度の高い部屋では、シリカゲルなどの乾燥剤と一緒に保管すると効果的です。また、絵の具を長期間使用しない場合は、元の容器ごとジッパーバッグに入れる、密閉ケースにまとめて保管するなど、湿気対策を強化すると安心です。
捨てるべきタイミング
絵の具の劣化にはいくつかのサインがあります。例えば、フタを開けたときに異臭がする、内容物が分離していて混ぜても元に戻らない、粘度が極端に変化していたりカビのような斑点がある場合は、使用を避けて廃棄を検討しましょう。アクリル絵の具や油絵具が完全に固まっている場合や、明らかに塗り心地や発色に異常がある場合も同様です。安全性や作品の品質を守るためにも、使えるかどうかを見極める目を持ちましょう。
使い切るための工夫
絵の具を無駄にせず使い切るには、計画的な使い方とちょっとした工夫がポイントです。必要な分だけを少量ずつ出して使うことはもちろん、余った絵の具で抽象画や実験的な作品を描く、色を混ぜて新たな色味を試すなど、創作の幅を広げながら消費していくことも可能です。また、使いきれそうにない色は、絵を描く仲間や学校、地域のアート活動をしている団体に譲るのも良い方法です。共有・活用することで、絵の具が最後まで活かされます。

