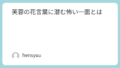「間違い」と「間違え」、どちらも似たような言葉ですが、実は使い方が異なることをご存じですか?日常会話やビジネスシーンで誤用してしまうと、思わぬ誤解を招くこともあります。
本記事では、それぞれの意味や正しい使い方を詳しく解説し、間違いなく使いこなせるようにサポートします。文章を書くときに迷わないためにも、ぜひ参考にしてください!
間違いと間違えの意味の違い

間違いとは?その具体的な意味
「間違い」は名詞であり、「誤り」「ミス」「不正確なこと」「勘違い」などを意味します。人が判断や行動を誤ったときに使われ、結果として誤った情報や行動が生じた場合に適用されます。
「間違い」は日常生活やビジネスシーン、教育現場など様々な場面で使われます。例えば、学校のテストで解答を誤ることや、ビジネスで情報を誤解すること、友人との約束の日時を勘違いすることなどが挙げられます。
例:
- テストでいくつかの間違いをしてしまった。
- 彼の説明には事実誤認の間違いが含まれていた。
- 日本語の文法の間違いをなくすために勉強する。
- 予定の日付を間違えてしまい、友人との約束をすっぽかした。
また、「間違い」という言葉は、「間違いなく」や「間違いがない」などの表現としても使われ、確実性を強調する役割を果たすこともあります。
間違えとは?その具体的な意味
「間違え」は動詞「間違える」の連用形で、「誤る」「ミスをする」「取り違える」といった動作を表します。「間違い」と異なり、動詞として用いられるため、文章の中では特定の行為を指す場合に使用されます。
例えば、選択肢を誤ること、情報を取り違えること、道順を誤ることなど、何らかの具体的な行動に関連するミスを表現する際に使われます。
また、「間違え」は他動詞であり、目的語を伴って使用されるのが特徴です。そのため、「間違えた」といった形で結果を示したり、「間違えて」として動作の流れを示したりします。
例文:
- バスの乗り場を間違えた。
- 答えを間違えてしまった。
- 彼の名前を間違えて呼んでしまった。
- 提出する書類を間違えないように注意する。
- 私は駅を間違えて降りてしまい、遅刻した。
このように、「間違え」は具体的な動作を示す表現として、日常生活のさまざまな場面で使われます。
両者の定義を比較する
「間違い」は「誤り」という状態や結果を指し、「間違え」は「間違える」という動作や行為を指します。つまり、「間違い」は事象として存在し、「間違え」はその行為を指すため、文の構造や意味が異なります。
- 「間違い」は名詞
- 「文法の間違いを指摘する。」
- 「これは過去最大の間違いだった。」
- 「彼の発言には多くの間違いが含まれていた。」
- 「間違え」は動詞(間違える)の連用形
- 「駅の出口を間違えてしまった。」
- 「彼の名前を間違えないように気をつける。」
- 「重要な情報を間違えたせいで、誤解が生じた。」
また、具体的な使用例を見ても、両者は異なる役割を持っていることがわかります。
- 「間違いを直す」と言うことはできますが、「間違えを直す」とは言いません。
- 「レポートの間違いを修正する。」(正しい)
- 「レポートの間違えを修正する。」(不自然)
- 「間違えた答え」とは言いますが、「間違いした答え」とは言いません。
- 「テストで間違えた答えを見直す。」(正しい)
- 「テストで間違いした答えを見直す。」(不自然)
このように、「間違い」は名詞として結果や状態を表し、「間違え」は動詞の連用形として具体的な行為を示すため、それぞれの適切な使い方を理解することが重要です。
間違えるって、怖いよね。
でもね、本当に怖いのは、間違うことじゃなくって、間違えを認められないことなんだよ。
間違いから目を背けちゃうと問題点まで見えなくなっちゃう。
間違えて良い。
間違いを放置だけはしないでね。— 難波武尚 (@takehisananba) January 29, 2025
間違いと間違えの使い方
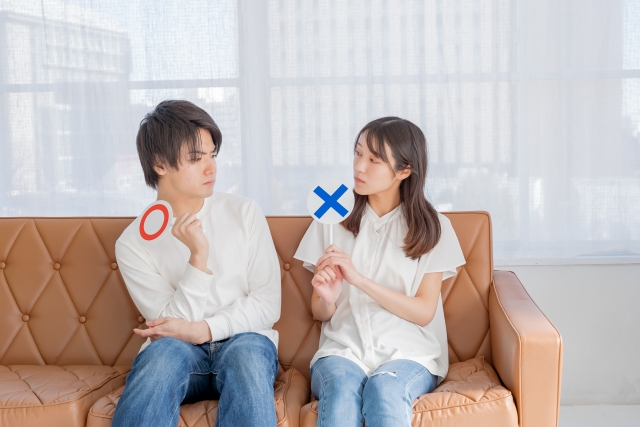
間違いの使い方の例文
- 彼のレポートには多くの間違いがあった。
- これはよくある間違いです。
- 文法の間違いを減らすために勉強する。
- 彼の計算には致命的な間違いがあった。
- 方向を間違えると、目的地に到着できない。
- 彼女は間違いなく正しい情報を伝えた。
- プログラムのコードに小さな間違いがあり、動作しなかった。
- 歴史の間違いを訂正することが重要だ。
- この看板の表記には誤字という間違いが含まれている。
- 子どもたちはゲームのルールを間違いなく理解できるように説明を受けた。
- 契約書の間違いを見逃さないように注意しよう。
間違えの使い方の例文
- 彼は答えを間違えた。
- 名前を間違えて呼んでしまった。
- 道を間違えたせいで遅刻した。
- メールの送信先を間違えてしまい、重要な情報が別の人に届いた。
- 予約の日付を間違えたため、キャンセル料を支払うことになった。
- 会議の開始時間を間違えて、遅刻してしまった。
- 彼女の誕生日を間違えてしまい、プレゼントを渡すタイミングを逃した。
- レシピの分量を間違えてしまい、料理の味が変わってしまった。
- 友人の電話番号を間違えて登録し、別の人に連絡してしまった。
- 重要なパスワードを間違えて入力し続け、アカウントがロックされた。
言い間違いの具体例
- 「間違いない」と「間違えない」を混同する。
- 「違いない」と「違えない」を誤用する。
- 「確実だ」という意味で「間違えない」を使ってしまう。
- 「間違えないでください」と言うべき場面で「間違いないでください」と誤用する。
- 「覚え間違い」を「覚え間違え」と表現する。
- 「聞き間違い」を「聞き間違え」と誤って言う。
- 「見間違い」と「見間違え」を混同する。
- 「選択ミス」を「選択間違え」と誤って表現する。
- 「問題の間違い」を「問題の間違え」としてしまう。
- 「発音の間違い」を「発音の間違え」と言ってしまう。
間違いと間違えの原因
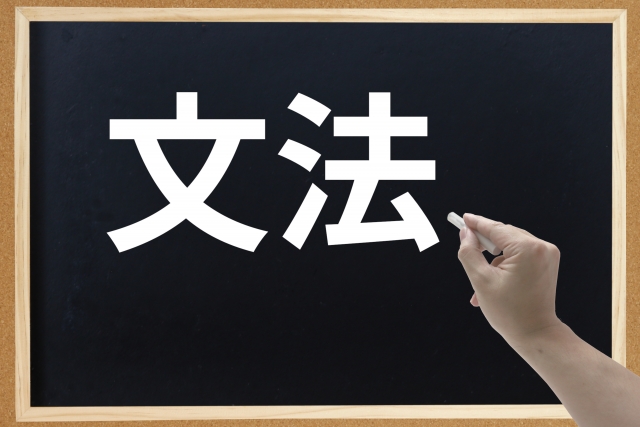
言い間違いが多い理由
- 似たような音の言葉が多い。
- 例:「間違い」と「間違え」、「違い」と「違える」など、発音が似ているため混同しやすい。
- 「覚え間違い」と「覚え間違え」のように、不適切な形で使われることがある。
- 自動詞と他動詞の使い分けが難しい。
- 日本語の動詞には自動詞と他動詞の区別があり、例えば「間違う」は自動詞、「間違える」は他動詞だが、これが正しく理解されていないことが多い。
- 例:「私は間違えた」ではなく、「私は答えを間違えた」とするのが正しい。
- 言葉の意味を曖昧に覚えている。
- 多くの日本語学習者や母語話者でも、文脈による使い分けを意識せずに言葉を覚えることが多い。
- 例:「間違いない」と「間違えない」の違いを明確に認識していないため、誤用が発生する。
- 「聞き間違い」と「聞き間違え」を混同するケースもよく見られる。
このような理由から、日常的に間違いが生じやすく、特に会話の中では瞬時に適切な言葉を選ぶことが難しいことがある。
最近「間違い」と「間違える」の使い方が分からなくなってゲシュタルト崩壊みたいになってる
例えば、「間違いたくない」は「間違えたくない」じゃないの?
「書き間違え」とかの○○間違え系、「書き間違“い”」じゃないの?
「間違いないように」は「間違えないように」じゃないの?
などなど
— なつ (@chimuhan055) January 29, 2025
行為としての間違いの要因
- 知識不足による誤認。
- 注意不足によるミス。
- 習慣的な誤用。
自動詞と他動詞の違い
「間違える」は他動詞であり、目的語を伴って使用されます。他動詞は動作の対象(目的語)を明示する必要があるため、「何を間違えたのか」を明確にする必要があります。
- × 「私は間違えた。」(何を間違えたのか不明確)
- ○ 「私は答えを間違えた。」(目的語があるため適切)
- ○ 「彼は電車の時間を間違えた。」(「電車の時間」が目的語)
- ○ 「彼女はメールの宛先を間違えた。」(「メールの宛先」が目的語)
一方、「間違う」は自動詞であり、目的語を取らずに単独で使用することができます。自動詞は主語の動作が完結するため、何を間違ったのかが文脈から推測されることが多いです。
- ○ 「私は間違った。」(間違いの内容は文脈から判断)
- ○ 「この答えは間違っている。」(状態を示す)
- ○ 「彼は道を間違った。」(道順に関してのミスを表す)
- ○ 「計算が間違っている。」(「計算」という結果が誤りであることを示す)
また、「間違う」は状態の説明としても使われるため、「この選択は間違っている」「彼の考えは間違っている」といった表現が可能ですが、「間違える」ではそのような用法はありません。
このように、「間違える」は目的語を伴い具体的な誤りを示し、「間違う」は目的語なしで誤りの状態を表すことができる点が大きな違いです。
間違いと間違えの連用形

間違いの連用形の説明
「間違い」は名詞なので、連用形の概念はありませんが、修飾語として使うことができます。
- 間違いだらけの文章
- 間違いのない選択
間違えの連用形の説明
「間違え」は「間違える」の連用形で、「間違えて」「間違えた」と活用します。
- 彼は計算を間違えてしまった。
- 私は駅を間違えて降りた。
間違いと間違えの間違いない使い方

間違いないとはどういう意味か
「間違いない」は「確実である」「正しい」「疑う余地がない」という意味です。この表現は、確信を持って何かを断定する際に使われ、日常会話からビジネスシーンまで幅広く使用されます。
また、「間違いなく」という形で副詞的に使うこともでき、事実や結果を強調する際に用いられます。
使用例:
- 彼が犯人であることは間違いない。
- このレストランは美味しいに違いない。
- 彼の努力が実を結ぶのは間違いない。
- この方法を使えば成功するのは間違いない。
- 彼は間違いなく最適な選択をした。
- 君の判断は間違いなく正しい。
- このイベントは間違いなく大成功だった。
- 彼女は間違いなく素晴らしい才能を持っている。
「間違いない」は、根拠がある場合や、強い確信を持って発言する場面で特に有効な表現です。
間違えないの正しい使用法
「間違えない」は「誤らないようにする」「ミスを防ぐ」「慎重に対応する」という意味を持ちます。何かを実行する際に、間違いを起こさないように注意する、または正確に行うことを表現します。
この表現は、日常会話だけでなく、ビジネスシーンや学習環境など、慎重さが求められる場面でよく使われます。
使用例:
- 彼の名前を間違えないようにしましょう。
- ルートを間違えないために地図を確認する。
- 重要な契約書なので、内容を間違えないようにチェックしてください。
- 試験では答えを間違えないように慎重に解答しましょう。
- 料理のレシピ通りに作れば、間違えないで美味しく仕上がる。
- メールアドレスを間違えないように慎重に入力する。
- 公式な発表なので、事実を間違えないようにしましょう。
- プレゼンのスライドに誤字がないか、間違えないように確認する。
- 友人の誕生日の日付を間違えないように、手帳にメモをしておく。
このように、「間違えない」は、特に注意が必要な行動や、正確性が求められる状況で頻繁に使われる表現です。
間違いと間違えの誤り一覧

よくある間違い examples
- 「間違い」と「間違え」の混同
- 例:「文法の間違いを指摘する」と「文法を間違えた」の混同
- 「間違いない」と「間違えない」の誤用
- 例:「この情報は間違えない」と言うべきところを「この情報は間違いないでください」と誤用
- 「間違いなく」と「間違えなく」の誤用
- 例:「間違いなく成功する」と言うべきところを「間違えなく成功する」と誤用
- 「聞き間違い」と「聞き間違え」の誤用
- 例:「彼の話を聞き間違いした」と言うべきところを「聞き間違えした」と誤用
- 「書き間違い」と「書き間違え」の混同
- 例:「書き間違いが多い」と言うべきところを「書き間違えが多い」と誤用
- 「言い間違い」と「言い間違え」の混同
- 例:「彼の言い間違いを指摘する」と言うべきところを「彼の言い間違えを指摘する」と誤用
- 「見間違い」と「見間違え」の混同
- 例:「標識を見間違いした」と言うべきところを「見間違えした」と誤用
間違いが起こらないための方法
- 言葉の意味を正確に理解する。
- 実際の使用例を確認する。
間違いと間違えの問題点

間違いによる混乱の事例
文法や語彙の誤りが原因で、誤解や混乱が生じることがあります。特に公の場面やビジネスシーンでは、些細なミスが大きな問題へと発展することも少なくありません。
例えば、契約書や公式文書で文法の間違いがあると、法的な意味が変わり、誤解を招く可能性があります。また、プレゼンテーションやスピーチの際に言い間違いをすると、意図した内容とは異なる印象を与えてしまうことがあります。
日常会話でも、似た音の言葉を間違えることで相手に誤解を与えることがあり、時には人間関係にも影響を及ぼすことがあります。例えば、「間違いない」と「間違えない」の使い分けを誤ると、発言のニュアンスが変わり、伝えたい意図が正しく伝わらないことがあります。
このように、間違いが引き起こす混乱はさまざまな場面で発生するため、言葉を正しく使うことが重要です。
訂正の必要性
言葉の誤りは、時間が経つと無意識のうちに定着しやすくなります。そのため、早い段階で誤った表現を訂正し、正しい言葉遣いを身につけることが重要です。特に、教育やビジネスの場面では、誤った言葉遣いが信用を損なう要因となることもあります。
例えば、書類やメールで誤った日本語表現を使用すると、相手に誤解を与えたり、プロフェッショナルな印象を損なったりする可能性があります。また、日常会話においても、間違った言葉を使い続けることで誤解が生じたり、適切な意図が伝わらなかったりすることがあります。
そのため、言葉の訂正は単なる間違いの修正ではなく、正確な情報を伝えるための重要なプロセスです。誤った表現が広まらないようにするためには、誤用を指摘し、適切な言葉遣いを意識することが大切です。また、間違いを指摘された際には、訂正を受け入れ、正しい表現を学ぶ姿勢が求められます。
正確な日本語を使用することで、より円滑なコミュニケーションが可能になり、誤解を防ぐことにもつながります。
間違いと間違えの重要性

日本語における言葉の重要性
日本語における言葉の使い分けは、正確なコミュニケーションを実現するために非常に重要です。言葉の誤用があると、意図が正しく伝わらず、誤解や混乱を招くことがあります。特に、フォーマルな場面やビジネスの現場では、適切な表現を用いることが信頼性や専門性を示す要素となります。
正しい表現の必要性
正しい日本語を使用することで、誤解を防ぎ、スムーズな意思疎通が可能になります。例えば、敬語や丁寧語を適切に使うことで、相手に対する敬意を表し、円滑な人間関係を築くことができます。また、言葉の意味や用法を理解することにより、より説得力のある話し方や文章を書くことができるようになります。
言葉は単なる情報伝達の手段ではなく、社会的な関係を築く重要な要素です。適切な表現を身につけることで、相手に信頼されるだけでなく、自分の考えや意図を的確に伝える能力も向上します。
間違いと間違えについての質問

よくある質問と回答
言葉の違いに関する疑問は多くの人が持つものです。以下に、よくある質問とその回答を詳しく説明します。
Q: 「間違い」と「間違え」の違いは? A: 「間違い」は名詞であり、誤った状態や結果を指します。一方、「間違え」は動詞「間違える」の連用形で、誤るという行為そのものを示します。
例:
- 間違い: 「このレポートにはいくつかの間違いがある。」(誤った箇所を指す)
- 間違え: 「彼は答えを間違えてしまった。」(誤るという動作を表す)
Q: 「間違いない」と「間違えない」の使い分けは? A: 「間違いない」は「確実である」「正しい」という意味を持ちます。一方、「間違えない」は「誤らないようにする」「間違いを避ける」という意味を持ちます。
例:
- 間違いない: 「彼が優勝するのは間違いない。」(確実にそうなるという意味)
- 間違えない: 「試験では答えを間違えないように気をつけましょう。」(誤らないように注意するという意味)
このように、それぞれの言葉の使い方を正しく理解することで、適切な表現を選ぶことができます。
間違いに関する相談事例
日常生活や仕事の場面で、「間違い」と「間違え」のどちらを使うべきか迷うことはよくあります。特に、文章を書く際には、どちらの表現が適切なのか判断に困ることがあります。
例えば、ビジネスメールや報告書などの正式な文書では、「間違い」が適切な場合が多いですが、会話の中では「間違えた」と動詞の形で使うことが一般的です。
また、口語と書き言葉での使い分けも重要です。話し言葉では「答えを間違えた」や「道を間違えた」といった表現が自然ですが、書き言葉では「誤りを修正する」「誤解を解く」など、別の表現に置き換えたほうが分かりやすいこともあります。
このように、場面や文脈によって適切な表現を選ぶことが大切です。
これらのポイントを押さえて、正しい日本語を使うようにしましょう!